JASジャーナル目次
2025
- JASジャーナル
Vol.65 No.3
-

- OTOTEN2025を終えて
- 一般社団法人日本オーディオ協会 会長 小川理子
毎日暑い日が続いておりますが、皆様方におかれましてはお変わりございませんか。 さて、OTOTEN2025は、前年比140%の8650名の来場者をお迎えして、無事に終了いたしました。これもひとえに、出展企業の皆様方、ご関係…
-
- OTOTEN2025特集
-
- OTOTEN2025開催報告 日本オーディオ協会 事務局 八木真人
- 音を使った観光誘致
OTOTEN2025で立体音響デモ 千葉工業大学 未来変革科学部 関研一
-

- オーディオと聴能形成の接点
- 九州大学 大学院芸術工学研究院 音響設計部門 准教授 河原一彦
この文書の読者は,「音」ということばを見聞きしたときに、何を想像するでしょうか?この問自体を不思議に感じる方もいらっしゃると思います。本稿では、聴能形成について概説しますが、その前提となる大切なことを説明します。
-

- 東京藝術大学 音楽環境創造科における聴能形成
- 東京藝術大学 音楽環境創造科 教授 丸井淳史
聴能形成は、「音に対する鋭い感性」つまり「音の違いを生じさせる音響特性の違いまでを正確に認識し、適切に表現できる能力」(参考文献3:北村ら, 1996)を向上させるための訓練です。
-
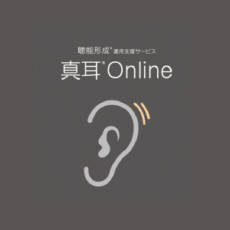
- 聴能形成の広がりと今後の展望について
~訓練サービス運営の視点から~ - 日本音響エンジニアリング株式会社
ソリューション事業部 事業部長 森尾謙一 聴能形成の歴史は長いですが、音の聴かれ方、音に関わるサービスの変化によって、聴能形成へ向けられる期待も変化し、今なお広がりを見せています。本稿では、聴能形成運用支援サービス「真耳Online」の運営側からみた聴能形成への期待の変化、課題、これからの聴能形成についてまとめています。「真耳Online」で行われていることを通して、今、聴能形成がどうなっているのかを追ってみたいと思います。
- 聴能形成の広がりと今後の展望について
-

- ミュンヘン・ハイエンド2025見学記
- 日本オーディオ協会 事務局 関英木
今年4月より日本オーディオ協会へ入職しました私、関英木が、ミュンヘン・ハイエンド2025を視察してきましたのでレポートさせていただきます!昨年の末永専務理事のレポートと合わせて読んでいただければ、より深く理解できるものと…
-

- 個人会員に聞く!
第10回 山﨑雅弘氏 - インタビュアー 末永信一(専務理事)
今回の「個人会員に聞く!」は、元パナソニックの音響設計者であり、現在は『楽音倶楽部(らくおんくらぶ)』を立ち上げられ、オリジナルのオーディオアクセサリー製品の開発を行うと共に、コンサルタントや講演活動などもされております山﨑雅弘さんにお話を伺ってまいりました。
- 個人会員に聞く!
-

- JASインフォメーション
・2025年 通常総会 報告
・2025年度 第1回 理事会/運営会議 報告
-

- こちらJASジャーナル編集局
JASジャーナル発行に携わる編集委員と事務局のメンバーが、日々思ったことを自由気ままに呟きます。




